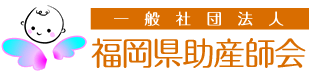2024年度 福岡県助産師会 活動目標 スローガン
<2023年度の活動評価と2024年度活動目標>
福岡県助産師会は、社会の変化に対応できる組織づくりを目標に、活動スローガン“つながるいのち、ひと、組織”を掲げ、組織改革、連携強化に努めてきました。
2023年度はCOVID‐19が5類感染症に移行しました。理事会は対面で行い、研修もハイブリッドや対面を増加し、活動を拡大していきました。研修は、時代のニーズに沿ったテーマ設定と日本助産師会の研修システムを導入することにより、全国から多数の申し込みがあり、成果を上げることができました。委託事業は順調な伸びを遂げ産後ケア事業の市町村との契約は23市町に増加しました。
さらに、2023年は2024年に開始する新事業の準備を行いました。すなわち、包括的性教育事業プロジェクトメンバーによる「助産師が伝える包括的性教育・いのちの教育研修」の準備を、また4月から開始予定のSOS電話相談、福岡県プレコンセプションケアセンターの開所にあたって労務士や新しい事務の雇用等、体制強化に努めました。
ポストコロナの時代を迎え、今後は活動の幅をますます拡大していきます。引き続き組織改革を行い、かつ外部団体との連携を深め、多くの人々に助産師会の活動を知っていただけるよう広報の強化に努めます。母子保健を軸に、すべてのライフステージにかかわる助産師としての専門性に裏付けられた活動の発展を推進します。
<2024年度スローガン>
つながるいのち、ひと、組織
<2024年度 目標>
専門性に裏付けられた助産師活動の推進と専門性の向上を図る
<趣 旨>
福岡県助産師会は、会員が心を一つにし、スローガン・目標のもとに、活動目標の実現に向け活動します
<2024年度 活動目標>
1.組織体制を見直し、助産師活動の拡大・発展を図る。組織の再編:事業部門・事務部門の設置 事務・労務士の雇用
2.地域に根ざした助産活動を推進し、周知活動につとめる
1)妊娠・出産包括支援事業の拡大・推進
2)妊娠・出産にかかわる相談・教室及び女性の健康推進のための事業の活発化を図る
SOS電話相談 福岡県プレコンセプションケアセンター事業 包括的性教育事業
3.社会の変化に対応した専門的研修を実施する。包括的性教育研修 アドバンス助産師に関する研修
4.新会館を建設し、事業拡大に向け整備する
一般社団法人 福岡県助産師会 2024年度 事業計画
| 目標 | 行動計画 | 担当 |
| 1.助産及び母子保健事業の実施及び普及・啓発活動に関する事業 | ||
| 1.子育て・女性の健康支援事業が充実する | 1)働くママとパパのマタニティスクールの開催(福岡市委託事業) ①毎月2回、年間24回開催する ②スクール実施のための人材の確保と育成 ③感染対策の徹底 | マタニティスクール ワーキンググループ (福岡地区) |
| 2)オンラインウェルカムベビー教室の開催(北九州市委託事業) ①毎月1~2回、年間20回程度開催する ②他の母親教室に参加できない母子とその家族を支援する ③アンケート調査の実施 ④スクール実施のための人材の確保と育成 | 北九州地区 | |
| 3)マタニティ・ベビー講座講師派遣(スタジオアリス) ①毎月5~8回の講座の講師を派遣する ②人材の確保 | 子育て女性健康支援センター | |
| 4)妊娠・出産等に関わる相談支援事業(北九州市委託事業) ①電話相談を週5日(月~金曜日、9~17時)実施する ②実施ごとの評価の充実 | 北九州地区 | |
| 5)地域における子育てや女性の健康に関する相談事業の実施 ①電話相談を週6日実施する ②相談事業をHP、チラシ等を用いて広報する ③女性や母子を対象とした健康教育講座を開催する | 子育て・女性健康支援センター | |
| 6)助産師による妊娠から産後1年までの継続した子育て支援を行う 1)オンラインママパパ産後交流会を実施する 2)対面でのママパパ産後交流会を実施する 3)助産院や行政と連携して子育て支援を行う |
||
| 2.地域に根ざした母子保健活動を実施する | 1)妊婦健診公費補助事業の継続と充実 (県内55市町村と委託契約) | 受託会員 助産所部会 |
| 2)産婦健康診査事業の実施 (北九州市・春日市・那珂川市・飯塚市・嘉麻市・桂川町委託事業) | 受託会員 |
|
| 3)出産前後小児保健指導(ぺリネイタルビジット)事業の実施 (北九州市委託) | 受託会員 北九州地区 |
|
| 4)産後ケア事業の実施 (北九州市・みやこ町・遠賀町・水巻町・芦屋町・岡垣町・中間市・飯塚市・嘉麻市・桂川町・宮若市・宗像市・福岡市・糸島市・春日市・太宰府市・大野城市・筑紫野市・那珂川市・八女市・柳川市・大川市・みやま市より委託) | 受託会員 |
|
| 5)妊産婦、新生児訪問事業 (桂川町・柳川市・みやま市・大牟田市より委託) | 受託会員 筑豊地区・筑後地区 |
|
| 6)地区助産師の活動の活性化を図る ①地区会員のニーズを把握し、活動計画を検討し、理事会へ報告とともに提案する ②地域の母子のニーズを把握し、活動計画を検討し、理事会へ報告とともに提案する(筑後地区:子育てサロン事業協力、久留米地区:子育て相談事業協力・歯科医師や助産師による講話の実施) ③行政との連携を図る | 各地区理事 | |
| 3.災害発生に向けての備えを行い、発生時の対応が迅速に行え、妊産婦・女性の支援が充実する | 1)防災意識の向上に繋がる活動を行う ①災害対策に関する研修会に参加する ②委託事業担当時の発災について検討する(福岡市マタニティ教室等) | 災害対策委員会 |
| 2)災害時の連絡体制を整える ①災害対策マニュアルの見直しを実施した。令和6年度より、ホームページによる運用を開始予定。災害時マニュアルについて情報提供し、緊急時の連絡方法の周知徹底を図る ②日本助産師会による安否確認訓練(緊急時速やかに連絡がとれるように、連絡方法の簡素化、明確化を図る) ③九州沖縄地区災害対策委員会において、各県の災害対策委員長の連携強化のためLINEグループを利用し、速やかな情報交換を実施する。年間2回の定例会(ZOOM会議)開催予定。 ④災害時に他県(九州沖縄地区)から依頼があった場合にすぐに対応できるよう、福岡県助産師会内で支援体制のシステムを作成する ⑤災害時小児周産期リエゾンへ向けた県などの動向、依頼があればすぐ対応できるよう、研修会等があれば参加する。また助産所部会と協働し準備していく |
||
| 3)行政関連機関との連携 ①県・市町村に、災害時の母子や女性の支援の必要性と、支援者としての助産師の存在について情報提供を行う |
||
| 4)会館内の防火体制の設備管理 ①年2回の避難訓練の実施(7・1月) ②消火器の目視点検(7・12月)を行い、7月は点検報告書を消防署に提出する |
||
| 4.すくすく赤ちゃん献金活動への協力強化 | 1)献金箱の設置場所を増やし、積極的に募金活動を行う | 理事会 |
| 5.専門職能団体として社会の認識を高める | 1)広報活動 ①ニュースレターの発行と会員及び関連団体への送付 ②ホームページを充実させ、迅速な情報提供に役立てる ③インスタグラムにより、広く迅速な情報提供を行う ④TNCはじめてばこに福岡県助産師会のチラシを同包する ⑤助産師会ノベルティグッズの作成 ⑥九州交響楽団マタニティコンサートで助産師相談コーナーを担当する ⑦TVや広報誌の取材を受ける | 広報・渉外委員会 子育て女性健康支援センター |
| 2)国際助産師の日のイベント ①助産師活動と助産師会を伝える | 組織強化委員会 理事会 |
|
| 6.安心して、自信を持って妊娠、出産、育児が出来るよう支援活動を行う | 1)産後ケア事業の拡大・充実 ①福岡県内各市町村からの委託事業の獲得 ②各地区理事及び会員と情報を共有し、課題検討を行う。 ③委員会メンバー全員が訪問活動ができる様にマニュアルを作成 2)委託事業全般の見直しを行う 3)産後ケア事業受託者が各自治体の事業内容を熟知できる環境を整える ①ホームページに各自治体の契約内容や様式がダウンロード出来る様に作成する ②各自治体の契約内容及ぼ洋式の統一を福岡県担当者及び自治体との交渉を重ねる | 妊娠・出産包括支援委員会 |
| 2.次世代育成支援に関する事業 | ||
| 1.助産師による思春期教育を推進する | 1)思春期健康教室の開催(北九州市委託事業) ①小中学生を対象とした思春期健康教室の運営 ②性についての悩みを相談する場として助産師会が活用される | 北九州地区 |
| 2)思春期保健出前講座の開催(久留米市委託事業) ①小中学生を対象とした思春期健康教室の運営 ②性についての悩みを相談する場として助産師会が活用される | 久留米地区 | |
| 3)次世代の親づくり教育支援事業(春日市)への講師派遣 ①中学生を対象とし、講話と妊婦体験・赤ちゃん人形抱っこ体験を行う ②会員数名が見学を兼ね執務する | 筑紫地区 | |
| 4)性教育を行う会員助産師数を増やす ①教材の整備と貸し出しを行い性教育を実施できるよう整備する | 子育て・女性健康支援センター | |
| 3.リプロダクティブヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)の尊重、普及、活動に関する事業 | ||
| 1.助産師による女性のための健康増進を支援する | 1)電話相談 ①相談員のスキルアップを図る 2)女性を対象とする講座(Web)を開催する | 子育て・女性健康支援センター |
| 2.思春期・妊娠期・子育て期における人々の健康増進を支援する | 1)福岡県子育て支援電話相談事業補助金事業の交付をうけ,子育て支援電話相談事業を運営していく。 2)電話相談:月曜~土曜日(祝日含む) メール相談:365日24時間 3)相談事業担当:相談員6名と事務員1名を雇用し,管理者を1名置く 4)相談事業の内容:妊娠に関する相談,子育て支援,思春期相談とする 5)相談員は,常に新しい情報や知識を習得し,電話やメール対応の技能向上を図るための研修に参加する | 担当理事 常任理事 |
| 3.包括的性教育実践者を育成するための研修会を開催する | 1)助産師やその他専門職(看護師・保健師・行政・教員等)を対象とする包括的性教育研修会を月1回、計10回開催する ①性教育の歴史と助産哲学 ②今なぜ包括的性教育なのか? ③助産師が行ういのちの教育など10研修 2)①全10回の研修を対面により受講修了した福岡県助産師会会員は、福岡県助産師会包括的性教育認定講師として登録することができ、助産師会と契約している行政、学校等に派遣する ②福岡県プレコンセプションケアセンターでの相談に対応する。 | 包括的性教育ワーキンググループ プレコンセプションケアセンター |
| 4.思春期からの生殖可能年齢にあるすべての人々が、性と健康に関する正しい知識とライフスキルを身につけ、健康でより豊かな人生を送ることができるよう支援する | 福岡県プレコンセプションケアセンター事業 ①相談対応:電話相談・メール相談・来所相談を週5回実施する(日~木曜日) 医師の相談が必要と判断&希望者に対し医師オンライン相談へ繋ぐ ②研修会:各保健所9か所で、養護教諭等に、プレコンセプションケアに関する研修会を開催する ③出前講義:大学・専門学校生にプレコンセプションケアに関する講義を実施する ④情報発信:Instagram、HP、マンガ等を用いて広報を行う | プレコンセプションケアセンター |
| 4.助産業務の質の保証、並びに助産師の育成及び資質の向上に関する事業 | ||
| 1.専門職業人としての継続教育を支援する | 1)研修会の開催 助産師の専門的知識・技術の向上をめざし、さらにCLoCMiPレベルⅢおよび産後ケア実務助産師に対応した研修会を10回(オンデマンド6回、対面4回)開催する 研修内容 【オンデマンド研修】 ①助産哲学 講師:福岡県助産師会会長 佐藤香代 ②ハイリスク新生児ケア 講師:久留米大学病院、新生児集中ケア認定看護師 坂田理絵 ③0歳からの歯科 講師:いまばやしデンタルオフィス 山下総太郎 ④乳腺炎の対応(福岡県助産師会会員無料)講師:青葉台母乳ケアハウス 永田優子 ⑤⑥産後の身体について 講師:ブルームカイロプラクティック 山口康太 【対面研修】 ①会陰保護術 講師:お産の家 よつ葉 ②NCPR 講師:北九州医療センター ③BEAMS1虐待防止 講師:聖ルチア病院 神薗淳司医師 ④BEAMS2虐待防止 講師:聖ルチア病院 神薗淳司医師 | 教育委員会 |
| 2)日本助産師会の活動への参加 ①第80回日本助産師学会に参加する ②専門部会、地区研修会、各種研修会に参加する | 会長 関係役員 | |
| 3)開業助産師の専門職としての質を高める研修会の開催 | 三部会 | |
| 2.医療法を遵守した開業者の安全管理を徹底する | 1)安全対策 ①助産所の安全管理・機能評価を実施する ②安全管理指針の周知及び管理徹底の促進をはかる ③ガイドラインの周知とガイドラインに沿った業務遂行 ④部会間の問題共有と解決策・症例検討会の実施 ⑤助産所自己評価・他者評価実施 | 安全対策委員会 助産所部会 保健指導部会 勤務助産師部会 |
| 2)安全対策スキルアップを図る ①安全管理研修会を開催する ②三部会合同事例検討会の開催 |
||
| 3.医療事故調査制度の周知並びに支援団体としての役割を確立する。 | 1)医療事故調査制度に関する説明会実施 2)医療事故調査制度担当者選任と具体的な役割の確立 | 安全対策委員会 助産所部会 保健指導部会 勤務助産師部会 |
| 5.助産及び母子保健の調査・研究に関する事業 | ||
| 1.助産所の安全管理に関するデータが収集・活用される | 1)助産所部会 ①助産所が全国助産所分娩基本データ収集システムに参加し、各助産所がデータの入力を実施する ②分娩と母体搬送事例のデータ集積を行い、理事会と日本助産師会への報告を正確に行う | 助産所部会 |
| 2.子育て・女性健康支援センター事業のデータが収集・活用される | 1)電話・オンライン・対面による相談の内容をデータ化し、分析することで、子育て相談の動向や課題、女性が抱える健康課題等を明らかにする | 子育て・女性健康支援センター |
| 3.保健指導に関する事例報告のデータが収集・活用される | 1)保健指導部会 ①新生児訪問の情報交換、事故事例、母乳育児支援のための情報収集を行う ②研修会の開催 | 保健指導部会 |
| 4. 助産及び母子保健の調査・研究の発展 | 1)助成事業:会員からの申し出により、理事会承認に基づき、母子保健の研究に対して1件2万円の範囲で助成を行う 2)研究倫理審査 ①研究倫理に関する研修会を行う ②研究倫理審査を行い、必要時提言する | 理事会 研究倫理委員会 |
| 6.その他前条(定款第3条)の目的を達成するために必要な事業 | ||
| 1.一般法人として会が維持発展する | 1)会員増に向けた活動 ①施設訪問、賛助会員の勧誘 ②学生の研修会・事業参加優遇制度の活用 ③助産師養成学校の学生にニュースレター送付、入会勧誘 ④非会員への地区交流会への参加促進 ⑤医療施設、行政へのリーフレット、助産所一覧の配布 ⑥会員の勤務先一覧の作成 | 組織強化委員会 常任理事・理事会 広報・渉外委員会 |
| 2)会員サービスの向上 ①研修会などの迅速な情報提供 ②ホームぺージを活用した各種申込や書式のダウンロード ③会員のニーズの把握 |
||
| 3)老朽化した会館の整備 ①最終案を策定する ②ワーキンググループによる新会館の運営・レイアウトを検討、決定していく | 会館整備特別委員会 |
|
| 2.関連団体との連携をとり、様々な事業を行うための環境整備をする | 1)関連団体との連携 ①福岡市子ども虐待防止活動推進委員会、福岡県HTL-V母子感染対策協議会、福岡母性衛生学会、医療事故調査等支援団体連絡協議会、福岡地区小児保健研究会、北九州市小児保健研究会、福岡県助産師活用推進協議会等の関連会議に参加する ②福岡県周産期医療協議会に出席し、母体搬送時の医療ホットラインの活用に向け働きかける ③母子保健情報交換会・交流会の開催 | 会長および関係役員 理事会 |
| 2)議員・行政への要望 ①行政(福岡県・福岡県内市町村)に出向き、助産師会の活動を説明する ②政策懇談会等に招かれれば参加し、関係性を築いていく ③要望書の提出 | 常任理事 妊娠・出産包括支援委員会 |
|
| 3)表彰に関する事業 ①各表彰基準に該当する会員を候補者として推薦する | 理事会 | |
| 3.会の維持運営が適切に行われる | 1)収益事業 ①駐車場賃貸事業 ②モデルハウス賃貸事業 ③ニュースレターへの広告掲載料 以上の事業より収入を得る | 理事会 広報・渉外委員会 |
| 2)委託事業に関する分担金の徴収 ①受託した会員は、一律5%の分担金を会に支払う ②委託事業に関する事務作業を整理し、合理化を図る |
||
| 3)専門家との顧問契約により、会の運営が適切に行われる ①弁護士 ②税理士 ③社会労務士 |
||